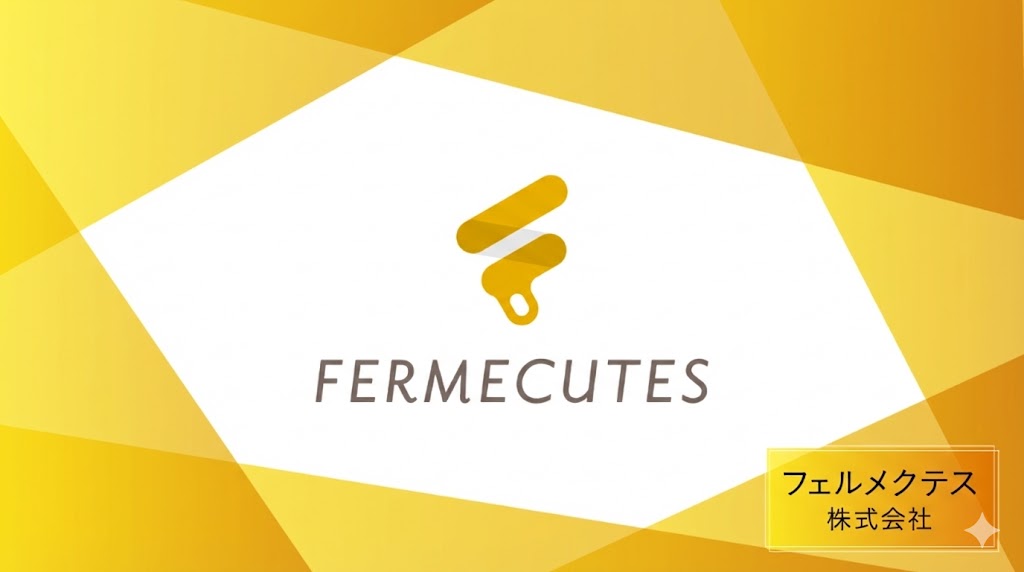
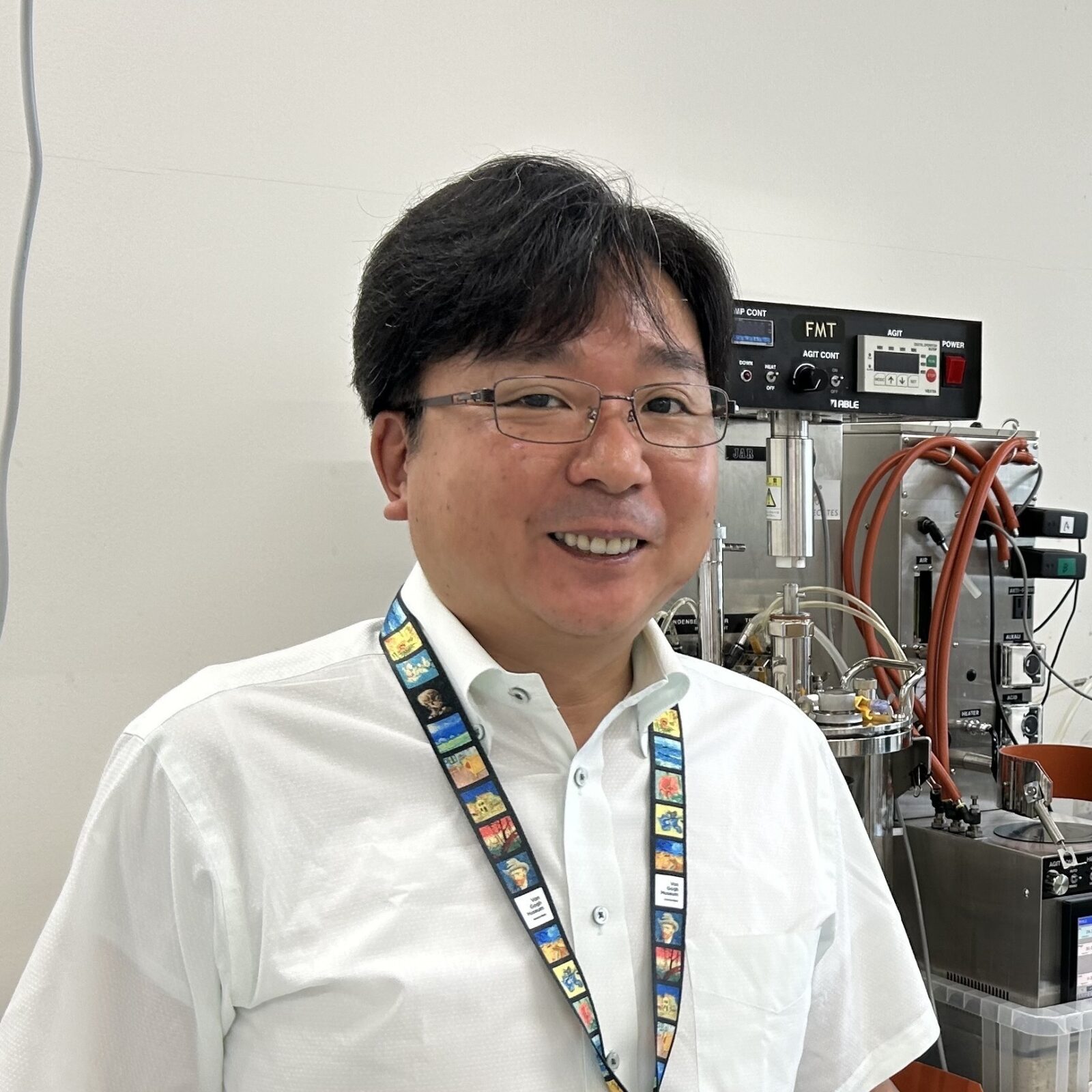
大橋 由明
フェルメクテス株式会社 代表取締役
慶應義塾大学先端生命科学研究所(IAB)を経て、大橋 由明氏が立ち上げたフェルメクテス株式会社が挑むのは、世界的なタンパク質不足の課題です。納豆菌を培養た、動物性でも植物性でもない高機能タンパク源「kin-pun®」の実用化。乳化作用や保水性に優れるこの独自技術を、ソリューションとして提供します。
本記事では、アカデミアからの起業を決断した大橋CEOに、「発酵性タンパク質」というアイデアの着想や創業ストーリーについて伺いました。
目次
───まず、フェルメクテス株式会社の事業内容について教えてください。
当社は「納豆菌を次世代のタンパク質源にする」ことに取り組んでいます。
具体的には納豆菌そのものを培養し乾燥させて、粉末化したものを加工食品に使用する技術開発を進めています。現状では、パンやお菓子関連に使用できると分かっているため、試験的に販売も行っています。
今後は生産技術と食品としての価値創造に注力し、世界中の加工メーカーにリーズナブルな価格で提供していくことを目指しています。納豆菌の価値は認識されてきているため、世界中の人々がタンパク質源として取り入れられるよう、培養や加工食品化のノウハウも展開していきたいと考えています。
───納豆菌というテーマに着目した理由と、その可能性について教えてください。
納豆菌は、私自身が学生時代から慶應義塾大学で教員をしていた頃まで、長年研究テーマとして扱ってきた微生物です。遺伝学的な取り扱いも含め、知識と技術はありましたが、まさか食品業界に進む人生になるとは考えていませんでした。
転機となったのは、SDGsの議論が加速し、世界的なタンパク質不足が深刻なテーマとして浮上したことです。タンパク質の偏在は既に飢餓を生み出しており、将来的には世界的な不足が懸念されています。日本国内でも高齢者のフレイル(虚弱)対策として、タンパク質の摂取が課題視されています。
そこで私が着目したのが、研究者として長年向き合ってきた「微生物を食べる」という発想の転換です。菌自体がタンパク質の塊であるならば、効率よく、そして摂取しやすいタンパク質として活用できるはずだと考えました。
───数ある微生物の中から、納豆菌を選んだ理由は何でしょうか?また、貴社の技術「発酵性タンパク質」を、専門知識のない人にも伝わるように教えていただけますか?
食経験の長い発酵菌である納豆菌、乳酸菌、麹菌の中から、最も適していると考えたのが納豆菌でした。非常に単純な構造をしていて増殖速度が非常に速いこと、そして多様なものを餌にできるポテンシャルがその理由です。これは、地球規模の食料課題を解決するための生産効率にも直結します。
また、「発酵性タンパク質」は私たちの技術の根幹にある概念です。微生物は非常に小さな存在ですが、生きていくための化学反応のほとんどをタンパク質が担っているため、その体内にはタンパク質が大量に蓄積されています。
発酵というと、醤油や納豆のように、微生物が食材を変換して美味しいものを作るイメージが一般的です。しかし、私たちの場合は、微生物自身が発酵活動によって自分の体、すなわち「タンパク質の塊」を作り出すと捉えています。

───ブランド「kin-pun®」開発の背景と、現在の利用シーンやターゲットについて教えてください。
納豆菌を培養した粉末を「kin-pun®」というブランド名で展開しています。日本人にとって納豆菌は「栄養価が高く健康に良い」というポジティブなイメージがありますが、納豆嫌いの人や、バクテリアである事実に抵抗を感じる人も少なくありません。
納豆菌そのものは納豆の味がしないため、味の連想からギャップが生まれる可能性も考えられたため、「納豆」という言葉を前面に出すのは適切ではないと考えました。
一方で、「微生物を食べる」という新しい食の認識を広げたい思いがあり、「菌の粉」を「金粉」と読ませる造語を採用しました。親しみやすさを持ちつつ、納豆のイメージから距離を置き、日本人が積極的に菌を食べていくポジティブなメッセージを込めています。
普段の食事に自然に取り入れられる形を目指しており、パンやパスタ、お団子などに入れることで、意識せずともタンパク質を摂取できるような形が理想です。老若男女問わず広く皆さんに食べていただきたいと考えていますが、高齢者向けの嚥下食のタンパク質摂取効率を高める用途や、子供向けの商品開発にも注力しています。
───ホエイプロテインなどの高タンパク質食材と比較して、「kin-pun®」の優れているポイントはなんでしょうか。
ホエイや大豆タンパク質にもそれぞれの良さがありますが、「kin-pun®」が大きく異なるのは、動物性でも植物性でもない、中間的な性質を持っている点です。アミノ酸組成も両者の中間に位置し、筋肉生成に良いとされる分岐鎖アミノ酸なども豊富に含まれています。
しかし、「kin-pun®」の決定的な優位性は、タンパク質を精製・抽出した粉ではなく、菌そのものを丸ごと摂取する点にあります。これにより、タンパク質以外のさまざまな付加価値をもたらします。パンにバターをからませやすくなったり、お菓子がより長持ちしたりと、食品に新たな機能性を付与できる唯一無二のタンパク質だと考えています。
また、一般的なタンパク質粉末は水に溶かすとべちゃべちゃになるのに対し、「kin-pun®」は水分量で硬さを調整できるため、お団子などの加工食品にも非常に適しており、用途の幅を広げやすいのも特長です。
───設立当初のメンバー構成、そして仲間たちが参加した経緯や、アイデアの着想について教えてください。
納豆菌を食べるというアイデアが生まれたのは、以前バイオベンチャー企業であるHMT時代の元上司から「微生物SDGsで新しい事業を考えてみて」と言われたのがきっかけです。世界的なタンパク質不足のテーマが目に留まり、「微生物なら納豆菌を食べればいい」というシンプルな発想に至りました。
自宅で思いつき、微生物の専門家である妻に相談すると、すぐに「面白い」と賛同してくれました。長年培養はしてきましたが、食べたことはなかったため、自宅で実際に焼いてみて食べられることを確認しました。
このアイデアを上司に相談すると即座に賛同してくれました。私は「こんな面白いアイデアなら誰かがやっているはずだ」と考え、特許などを徹底的に調べたのですが、見つからなかったのです。
そこで、当時最も大きな意思決定を担ってくれたのが、当時大手食品企業の役員で共同創業者となる児島氏です。彼は即決で「絶対面白い、俺も金出すから一緒に会社を始めよう」と断言してくれました。私と児島氏を中心に話を進め、HMT時代の同僚が経営管理に加わり、慶應IABと鶴岡工業高等専門学校の共同研究プロジェクトを経て会社を設立しました。
───最初期の顧客開拓と、その立ち上げ期に注力したことは何でしょうか。
最初の消費者ニーズ調査の動きとして、地元の食肉加工業者の社長様にすぐに相談に行きました。お肉屋さんである彼が次世代タンパク質をどう捉えるかを知りたかったのです。結果的に社長様は共同研究よりも出資したいと言ってくれ、特に食品ベンチャーを応援したいという彼の強い思いに助けられました。また、介護食メーカーの株式会社ベストと銀行の紹介で取り組みが始まりました。
しかし、初期は「kin-pun®」が加工食品として使用できる水準になかったため、すぐに取引を進めるわけにはいきませんでした。最初の3年間は、「食材としての確証」の確立に集中しました。具体的には、オリジナルの菌の作成、パンなどの試作による食材証明、特許取得、そして効率的な培養法の確立です。
OEM生産を念頭に、小さなタンクから生産体制を整えることを目標に掲げました。この立ち上げフェーズで、当初想定していなかった加工性や美味しさ、吸水性、腹持ちなどの付加価値が次々と見つかり、計画以上の成果につながりました。メーカーとの取引が始まったのは、この3年間を経てからです。
───その後の資金調達と、そこから学んだ教訓があれば教えてください。
設立当初は、経営陣やエンジェル投資家の個人的な出資で3年間を乗り切りました。転機は、特許を3本ほど出し、次の資金調達としてVCと話を詰めた時です。
交渉は進んでいたものの、VC側の要求とどうしても折り合いがつかず、一時は、事業の継続そのものが危ぶまれるほどの困難な状況に直面しました。去年の秋から冬にかけての出来事です。
その危機的な状況を救ってくれたのが、HMTの元社長様と現任社長様でした。当社の技術が双方に利益をもたらすと判断し、5,000万円を出資してくれたのです。その後、地元のフィデア銀行も参画を表明し、資金の繋がりができました。
この経験から、「事業の創設期にあたってはまず長期的な業務シナジーにコミットしてくれる事業会社からの出資を優先すべきだ」という重要な教訓を得ました。
VCは、双方の事業成長よりもキャピタルゲインが主たる目的であり、その可能性が高まればいつでもご出資頂けるからです。本質的に面白いアイデアであれば、みんな応援し、一緒にやってくれるという確信が持てました。
───長年、納豆菌の研究に携わっていた大橋さんが、起業の道を選ばれた経緯を教えてください。
大橋: 起業の道を選んだ最大の理由は、鶴岡にいたことにつきます。
私は、鶴岡サイエンスパークに慶應IABができた初期に移住しました。そこで多くのベンチャー企業が生まれる様子を見、またベンチャーで働いてきたため、自分で起業するという考えはなかったものの、ベンチャーに対する免疫はかなりありました。
もし不安があったら、おそらく起業はしなかったでしょう。アイデア自体は抜群に良いと確信していましたし、これはもう失敗しないという強い思い込みがありました。起業とは、そう思い込めないと始められないものです。
長年研究テーマとして扱ってきた納豆菌や枯草菌は、学会では有名でも用途は納豆製造や酵素生産などに限られていました。しかし、それが世界中の人に食べられて、食の最前線に上がっていくことは、研究者としての夢です。
将来的には、アフリカやインドの人々が納豆菌入りのパンを食べるようになり、「納豆菌は鶴岡からできた」というストーリーが実現すれば、多くの人が幸せになると信じています。
───起業後、研究者時代とは異なる「経営者」としての苦労や、やりがいを感じる場面はありましたか?
大橋: 会社を経営してみて、自分にはセンスがないなと痛感しました。株や資金調達、優先株などの話は、理屈は理解できても、全く面白いと感じないのです。
その部分を担ってくれるパートナーが、約1年半前に入社してくれたのは本当にありがたいことでした。彼も元々微生物が専門の研究者ですが、過去に務めていた日系大手企業で企業買収やM&Aなどを担当した経験があり、研究とは別の方面で会社に貢献してくれています。
───大橋さん自身が関わってこられたディープテック企業での経験は、現在どのような形で活きていますか?
大橋: ディープテック企業に関わってきた経験が活きる場面は多いです。特にHMTでは取締役も務めていたので、ベンチャーというものがどういうものかという理解もありましたし、普通の会社員だったら不安になるような場面でも動じないようになりました。
HMTの設立経緯は、研究者が特許や論文を発表し、VCが見つけて会社設立を提案したという非常にラッキーなケースでした。私たちのようにゼロから始めるのとは異なりますが、「製品や商品にインパクトがあったり、消費者がイメージできるものであれば、出資に繋がりやすい」という点は共通しています。
───大学発のスタートアップであることで良かった点、苦労した点について教えてください。
大橋: 慶應大学発であったことは非常に良かった点が多いです。設立当初、資金がなかった中で、大学が場所を提供してくれたり、使わなくなった機械を譲ってくれたりしただけでなく、学生はアルバイトで手伝ってくれるなど、皆さん協力してくれました。
また、鶴岡という地域性も重要です。鶴岡市は「食の都」でありながら、慶應発の食品ベンチャーがこれまでなかったため、私たちの会社がそのギャップを埋める存在として歓迎されました。
市民が応援したくなるようなベンチャーが生まれると、市や大学が支援するという良い連鎖が生まれます。医薬品などの難しい分野に比べ、食品であれば市民の理解を得やすく、応援してもらいやすいという利点がありました。
───今後フェルメクテスとしての新たな挑戦や目指す社会について教えてください。
大橋: 最終的な到達点は、「安いタンパク質源」を提供することです。いかにリーズナブルな価格で皆さんの手に届くようにするか。そのためには、生産効率の向上と、適切なタイミングでの設備投資が不可欠です。
私たちの野心的な目標は、世界のタンパク質摂取量の3割、具体的には1日60gのうち20gを納豆菌から摂取する社会の実現です。納豆菌という独自の文化を世界に売り出すことで、日本の価値を向上できる大きなやりがいも見据えています。
地球規模でのタンパク質貢献を目指すため、食品添加物のような形ではなく、主食として広く普及させることを考えています。
───目指す社会の実現に向けて、今後の具体的な活動と「kin-pun®」ブランドを浸透させる構想があれば教えてください。
大橋: 最優先事項は生産能力の向上です。具体的にはOEMの提携先を複数確保し、年間を通じて計画的に数トン単位で生産できる体制を固めること。そして内閣府のプロジェクトも活用し、OEMでは難しい、より効率的な連続バイオ生産装置を開発することです。
将来的には、鶴岡に一定規模の工場を建設し、日本国内に流通させる量を生産したいと考えています。一方でブランドの浸透については、まず鶴岡市の人全員に食べてもらうことを目指し、鶴岡から生まれたというイメージを定着させたいです。
そして、日本全体を考えると、大手食品加工メーカーに原料として採用してもらい、具体的な加工食品として店頭に並ぶことを目指します。今は、美味しいものをつくり、それを食べてもらう機会を増やすというフェーズに移行している段階です。
──────今後の技術応用として、食品以外の分野への進出の展望はありますか。
大橋: 現状は食品が主眼ですが、将来的にはペットフードや動物飼料への展開も視野に入れています。動物飼料は食肉生産の根源であり、人間が食べる穀物との競合もあるため、そこに応用できれば大きな意味があります。
また、化粧品分野についても研究開発を検討しています。納豆菌の成分が活用できるイメージがあり、天然素材としての価値提供の可能性があります。化粧品原料は単価が高いため、そちらを先にやるべきという意見もありましたし、実際にメーカーからの引き合いもあります。
戦略的にはまず食品で基盤を固めることが重要ですが、将来的に食品としてのイメージが浸透したタイミングで、化粧品への展開も実現したいと考えています。
───今後、仲間に加わってほしいステークホルダーを教えてください。
大橋: まずは、生産の大型化に向けて協力してくれるパートナーです。
日本が年間600万トンの小麦を消費することを考えると、自社工場のみで必要な生産体制は構築できません。
また、麹菌やユーグレナなど、新しい食品を開発している企業とのコラボレーションも重要です。微生物を食品にするという共通のテーマを持つことで、互いの価値を高められます。
大豆ミートを開発している企業とも相性が良く、競合というよりは、共に市場を作っていく仲間として協力したいと考えています。
今回、内閣府のプロジェクトで慶應義塾大学と山形大学が連携したことは、歴史的な出来事だと思っています。20年以上両者に交流がなかった中、当社が食品産業というハブになることができたのではと考えており、食の分野が大学同士を繋ぐ役割を果たすことができるのは嬉しい点です。
───資金調達や組織開発、競合企業の存在など、障壁となりそうなリスクは何が考えられますか?
大橋: まだまだ脆弱な経営基盤の中で、適切な時期に資金調達ができるかが最大のリスクだと考えています。技術開発を確実に進めて生産能力を向上させることで、市場拡大の可能性を示していく必要があります。
人材の課題もあります。山形県は人が集まりにくい地域なので、いかに組織を作り、優秀な人材を確保していくかが重要になります。
競合企業については、今のところほとんど出てきていません。
納豆菌を食べるというアイデアを思いついても、美味しく、効率的に作る技術の難しさから、簡単には参入できないのだと思います。特許も出しているので、他社が手を出せない状況もありますし、初期投資も非常に高額です。私たちはニッチな分野を攻めているからこそ、独自のポジションを確立できています。
───最後に、大橋さんと同じようにアカデミアからスタートアップに挑戦しようとしている研究者に向けて、メッセージをお願いします。
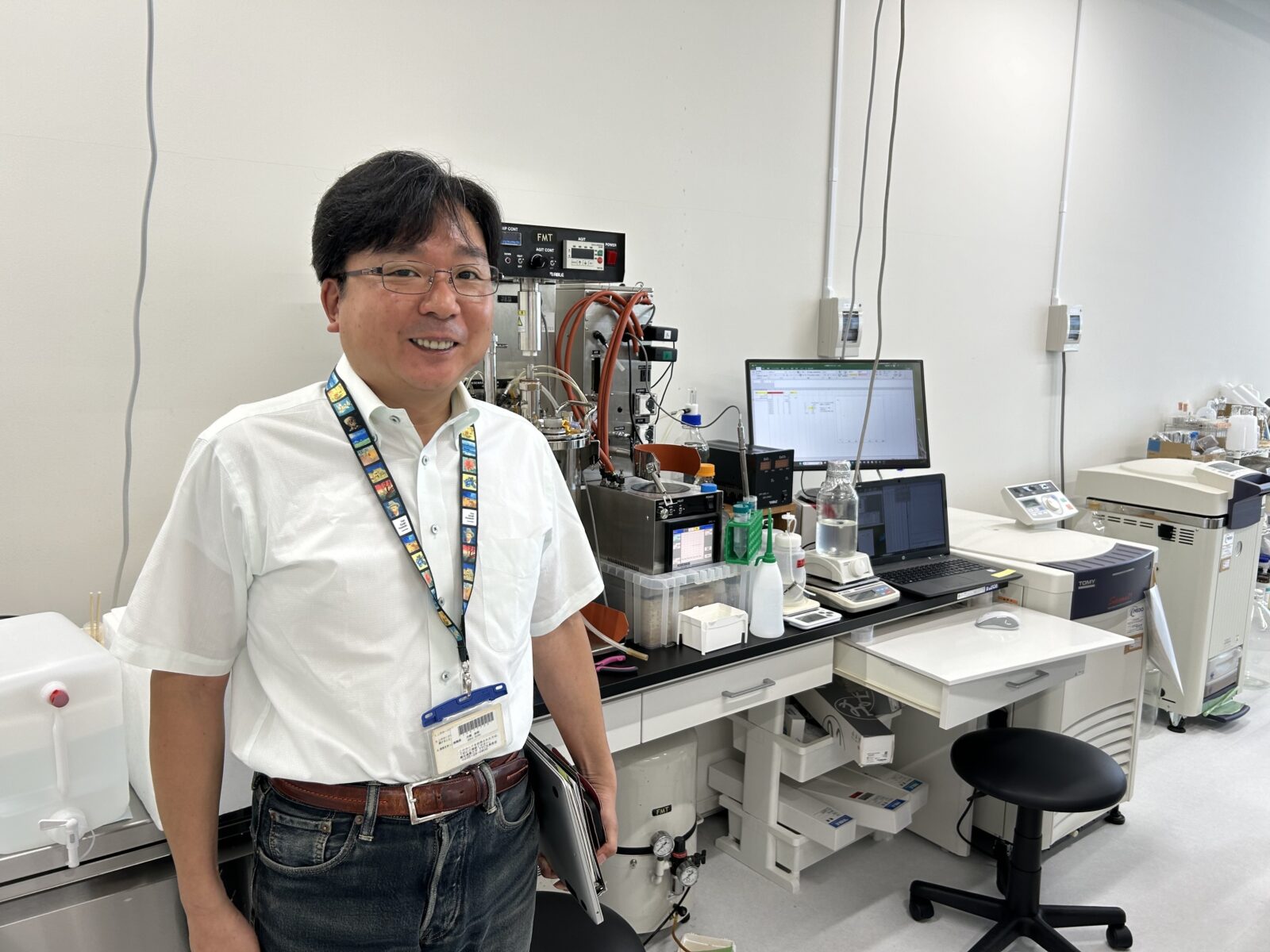
大橋: 私から経験を踏まえて伝えられるのは「研究者として、自分の研究が何の役に立つかを深く考えすぎない方が良い」というメッセージです。
応用を意識しすぎると、話が小さくまとまってしまう可能性があります。
基礎研究に没頭し、一生懸命取り組むことで、予期せぬ大きな価値が見つかることがあります。ノーベル賞受賞者の発見も、多くが偶然から生まれています。自分でイメージできることには限界があるため、多くの人と対話することで、新しい視点や可能性が見つかるかもしれません。
アカデミアからスタートアップに挑戦する際には、周囲の支援が不可欠です。私の場合、慶應義塾大学にいたからこそ、場所や設備、学生のサポートなど、さまざまな支援を受けられました。あるいは鶴岡のように、支援体制が整った地域での起業を検討するのも良いでしょう。
また、起業する自信が持てるまでは焦らないことが大切です。私自身は、アイデアに100%の確信が持てたからこそ始められました。
「本質的に面白いものだから、皆が応援し、一緒にやってくれる」という確信を持てるまで待つ。そして、食品分野のように支援者や、市民が応援したくしなるような事業を見つけることから始めるのも良いでしょう。
───本日はありがとうございました。