
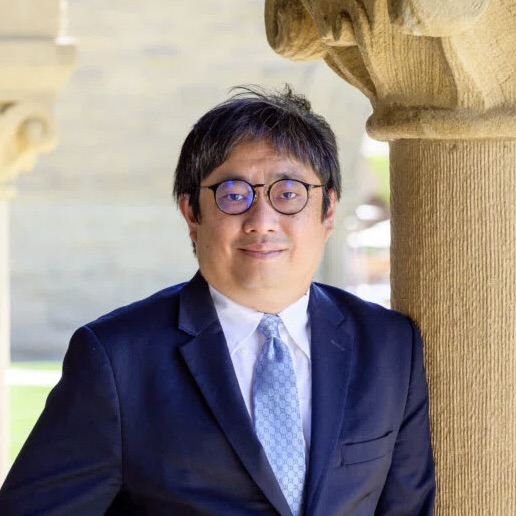
牧 兼充
早稲田大学ビジネススクール准教授
主な兼職として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)監事、カリフォルニア大学サンディエゴ校ビジネススクール客員准教授など。
【第1回】では、卓越した科学者がスタートアップを成功させる「スター・サイエンティスト」という概念と、彼らが置かれた日米の構造的な違いを分析した。【第2回】では、その理想的なエコシステムの姿・日本が抱える課題、そして未来への解決策を探る。
目次
では、理想的なエコシステムとは、どのような姿をしているのか。その問いに対する一つの答えとして、牧准教授が熱を込めて語ったのが、MIT(マサチューセッツ工科大学)のロバート・ランガー教授が率いる研究室、通称「ランガー・ラボ」の存在だ。コロナ禍においてmRNAワクチンという形で世界を救った企業、モデルナを生み出す直接のきっかけを作った、まさに「生ける伝説」である。
「ランガー教授の本質を理解する上で重要なのが、『パスツールの象限』という考え方です。研究は従来『基礎研究(純粋な知的好奇心)』と『応用研究(実用的な課題解決)』という二軸で分類されてきました。一方で「パスツールの象限」は、研究を「根底的な理解をめざすか」と「利用への応用可能性を目指すか」の二つの軸による4つの象限で分類します。ランガーは、根底的な理解を目指しながら、利用への応用可能性を目指す象限(パスツール型)で研究を実践しているのです」
多くの人が、「基礎研究で生まれた発見を、応用研究で製品化する」という直線的なイノベーション・モデルを想像する。しかし、ランガー・ラボの現実は、それとは全く異なる。
「彼らのアプローチは、むしろ逆です。応用研究、つまり企業や社会が直面している実務上の『尖った課題』を見つけ、それを解決しようと深く掘り下げる過程で、結果的に誰も知らなかったような新しい科学的発見、すなわち基礎研究のブレークスルーが生まれていく。そもそも基礎と応用に明確な境界線などなく、両者は常に相互作用し、螺旋を描きながら進化していくものだ、と。この『サイエンスとビジネスの好循環』を、研究室という一つの場で体現しているのが、ランガー・ラボの凄みなのです。これはまさに「パスツール型」の研究であるからできることです。」
そして、この好循環を回すために不可欠なのが、研究室の「外」との繋がりだ。
「彼らは決して研究室に閉じこもりません。重要なのは、その連携相手です。彼らが主に付き合うのは、安定した大企業ではなく、VCや、野心的な『尖った』スタートアップと連携して社会実装を推進するのです」
大企業から持ち込まれる課題は、既存事業の改善など、どうしても丸みを帯びがちだ。しかし、世界を根底から変えような研究は、スタートアップの方が相性が良い。
「モデルナのコア技術である『メッセンジャーRNAを薬として使う』という革新的なアイデアも、ランガーがもともと着想を得たものです。そして、そのアイデアをフラッグシップ・パイオニアリングというVCに持ち込み、『ベンチャー・クリエーション・モデル』という特殊なスキームで生み出されたのが、モデルナなのです」
多様な専門性を持つ研究者が集い、VCが頻繁に出入りし、尖ったスタートアップとの協業から常に新しい社会実装が生まれる。ランガー・ラボは、それ自体が「知」を「事業」へと変換し続ける、一つの巨大な永久機関のようなエコシステムなのである。
ランガー・ラボのようなダイナミックな知の好循環を、日本で生み出すことは可能なのか。牧准教授は、その実現を阻むいくつかの根深い「ボトルネック」の存在を指摘する。
「イノベーションは一度きりの線香花火であってはならない。持続的な『循環』でなければ意味がありません。その点で日本はループが閉じていない。アメリカでは、成功したスタートアップの創業者や初期の従業員が、母校である大学に多額の寄付を行う文化が根付いています。その寄付が次の世代のスター・サイエンティストを育み、新たな研究開発の種となる。この成功の果実が、次のイノベーションの土壌へと還元されるサイクルが、日本ではまだ非常に弱いのです」
そして、より深刻なのがエコシステムを構成する「人」の問題だ。
「特にディープテックの領域において、博士号(PhD)を持つ起業家、そしてベンチャー・キャピタリストが、日本では圧倒的に足りていません。これがエコシステム全体の『知のレベル』を致命的に下げてしまっている最大の要因だと私は考えています」
日本の理系のエリートコースは、長らく「修士課程を卒業し、大企業の研究所に就職する」というものだった。博士課程まで進むのはアカデミアに残るごく一部、という風潮がいまだ根強い。
「アメリカのディープテックVCでは、キャピタリストがPhDを持っているのはもはや常識です。そうでなければ、最先端の科学技術の価値を正しく評価し、リスクを見極めることなどできないからです。日本は社会全体がPhD人材の価値を信じていない。この人材輩出の構造が変わらない限り、エコシステムの規模と質の拡大には、自ずと限界が訪れるでしょう」
この博士人材の不足は悲しい帰結を生む。技術の深い理解者が経営層や投資サイドに少ないため、ディープテック・スタートアップが本来の技術開発を突き詰めることができず、目先のキャッシュフローのために受託開発やコンサルティングのようなビジネスに事業内容が「ずれて」いってしまう。それはVCの忍耐力の弱さや、一発のホームランが小さい日本の市場構造も相まって、日本のエコシステムが抱える根深い病理となっている。
エコシステムを構築するための仕組み作りもまた、道半ばだ。牧准教授は、アメリカで標準化されている起業家教育プログラム「I-Corps(アイコア)」を例に挙げる。
「I-Corpsは、NSF(全米科学財団)が主導する、いわば研究者向けのリーンスタートアップ実践プログラムです。教員、大学院生、そして外部のメンターが3者1組のチームとなり、徹底的に顧客インタビューを繰り返すことで、技術シーズの市場性を見極めていく。重要なのは、これがトップダウンで全米の大学に標準化されたプログラムとして提供されていることです」
これにより、アメリカのどこにいても、一定レベル以上の質の高い起業家教育を受けることができる。そして、プログラムの設計思想として実際に手足を動かす「大学院生」をチームに入れることが推奨されている点が、エコシステム全体の新陳代謝を促している。
「対して、日本の大学における起業家教育は、文科省の補助金などを活用し、各大学がボトムアップで、いわばバラバラに開発しているのが現状です。もちろん、各大学の努力は素晴らしいし実績をあげているのですが、なかなかノウハウが相互に共有されず、全体としての効率は良くない。何より、I-Corpsの前提となっているような、教員と学生がフラットなパートナーとして一緒に会社を作る、という文化が、日本ではまだ十分に醸成されていないことが大きな課題です」
インタビューの最後に、私たちは一つの問いを投げかけた。「スター・サイエンティストという言葉をもっとブランド化していくべきでしょうか?」と。それは、この概念を社会に浸透させるための戦略であると同時に、選ばれなかった研究者との間に新たな分断を生むリスクも孕んでいる。
牧准教授は、少しの間、思慮深く言葉を選び、そしてこう答えた。
「『ハイパフォーミングな研究者』と表現するよりも、『スター・サイエンティスト』という言葉の方がキャッチーで、イメージが湧きやすい。多くの人々にこの概念を広め、そういう生き方やキャリアパスが、もっとリスペクトされる文化を醸成する上では、非常に有効な言葉だと思います」
ただし、と彼は続けた。
「ただし、その使い方には細心の注意が必要です。『スター・サイエンティストになれなかった人は優秀ではない』というような、安易な二元論に陥ることだけは絶対に避けなければならない。あくまで、一つの概念として、イノベーションを目指すすべての研究者への希望となるような、そんな使われ方ができればと願っています」
スター・サイエンティストとは、特定の個人に与えられる栄誉ある「称号」ではない。
それは知の探求と社会実装という、長らく分断されてきた二つの世界を往還し、融合させようと挑戦する、すべての先駆者たちの生き様そのものを指す「概念」なのだ。それは日本の未来を切り拓くための、新しいロールモデルの提示でもある。
この記事を読んでいるスタートアップ経営者、あるいはこれから起業を志すあなたへ。
あなたの会社が今まさに直面している、誰にも解けない「尖った課題」。その解決の鍵は、意外にも近くの大学の研究室に眠っているのかもしれない。そして、あなたの事業にかける情熱とビジョンこそが、一人の研究者を「スター・サイエンティスト」へと覚醒させる、最初のトリガーになるのかもしれない。
牧准教授が解き明かした物語は、私たちに問いかけている。断絶の谷をただ眺めているのか、それとも、自らが橋を架ける第一歩を踏み出すのか。
日本のイノベーションの未来は、その一歩にかかっている。
【第2回】では、モデルナを生んだ「ランガー・ラボ」を例に理想的なエコシステムの姿を探り、日本が抱える「循環の欠如」「博士人材の不足」「起業家教育の分断」という3つのボトルネックを明らかにした 。【第3回】では、ディープテックにおける日米の連携モデルの違いを分析する。