
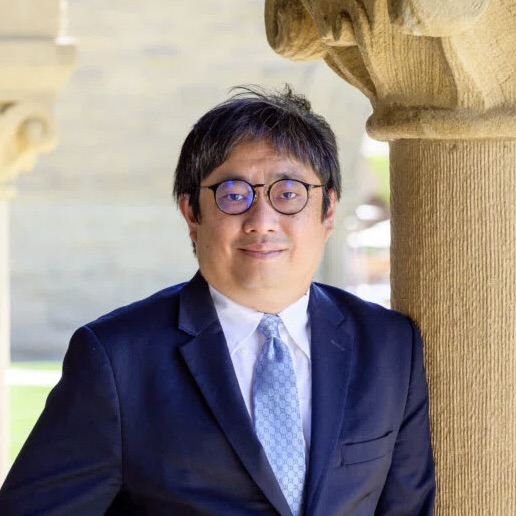
牧 兼充
早稲田大学ビジネススクール准教授
主な兼職として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)監事、カリフォルニア大学サンディエゴ校ビジネススクール客員准教授など。
【第4回】では、アカデミアで発展した「フィールド実験」などの科学的アプローチがビジネスの常識をどう覆すのか、そしてAI時代において真に求められる「科学的思考」の価値を解き明かした。【第5回】では、イノベーションの大前提となる「卓越した知」を生み出す博士人材が、なぜ日本で正当に評価されないのか、その構造的な問題に切り込み、「失われた30年」を終わらせる日本再生計画を提言する。
目次
我々はこれまでの記事で、イノベーションを生み出す「仕組み」の重要性と、それを乗りこなすための戦略、そしてアカデミアの知を社会実装する実践を追ってきた。しかし、これらの議論はすべて、ある一つの大前提の上に成り立っている。それは、国全体に「卓越した知」を生み出す人材が継続的に輩出されていることだ。
失われた30年──。日本の長期停滞の根源を辿ると、経済政策や産業構造の問題だけでなく、より根深い「知」そのものへの軽視に行き着くのではないか。特に、科学技術立国の基盤であるべき博士(Ph.D.)人材がこの国では正当に評価されず、その能力を全く活かしきれていない。
「なぜ、日本の博士人材は起業しないのか?」この問いに対し、牧准教授はその問題を「複合的だ」としながらも、2つの効果で説明できると語る。
「科学的に事象を分析する際、『トリートメント効果(Treatment Effect)』と『セレクション効果(Selection Effect)』という2つの側面から考えます。日本の博士が直面する問題は、まさにこの二重苦なのです」
この二重苦が、「博士はビジネスでは使えない」という「予言の自己成就」を生み出し、悪循環を固定化させている。
なぜ、このような歪んだ構造が生まれてしまったのか。その責任は、企業と大学の双方にある。
企業側の問題は、博士人材に対する待遇の低さだ。
「企業が博士を積極的に雇ってこなかった。それに加え、博士課程に3年以上を費やした分の価値を給与に上乗せしない。どう活用していいかもわからない。これでは博士に進学することが、キャリア形成における合理的な選択肢になりません」
ある政府の委員会で「博士の価値は5年で消える」という前提で制度設計がなされていたことがあった。博士課程で培われる「専門知識そのものではなく、未知の問題を解決するための科学的思考力や探求能力」というポータブルスキルへのリスペクトが、日本企業には決定的に欠如している。
一方、大学側の問題も根深い。
「米国では博士課程の学生は学費・生活費が支給されるのが一般的ですが、日本では経済的に余裕がないと進学が難しい。これにより、挑戦できる学生のプールが極端に狭まってしまっています」
結果として、博士課程は「研究者になりたい、経済的にも余裕がある、ごく一部の学生」だけが進む特殊なコースとなり、社会との接点を失っていく。
企業が博士を評価しないから、優秀な学生は博士を目指さないことが多い。博士課程が社会から孤立するから、企業で活躍できる人材が育たない。この「負のスパイラル」こそが、日本の「知」の基盤を静かに蝕んできた元凶だ。
この絶望的な状況下で、一つの光明がある。それは製薬業界だ。日本の産業界の中で、製薬業界は例外的に博士人材を積極的に採用し、重要な戦力として活用してきた。
「製薬業界は、常にグローバルな競争に晒されています。そのため、人材の採用や評価の仕組みも、必然的にグローバル基準にならざるを得なかったのでしょう」
この事実は、極めて重要な示唆を与えてくれる。日本企業も、真にグローバルな競争環境に身を置けば、博士人材の価値を再評価せざるを得なくなるということだ。逆に言えば、国内市場に安住し、同質的な人材でぬるま湯の競争を続けてきたことが博士人材、ひいては「知」そのものを軽視する風土を温存させてきたのである。
失われた30年からの脱却は、小手先の経済政策だけでは成し遂げられない。国家の競争力の源泉である「知」を生み出し、社会の隅々で活用できる仕組みへと国全体をリブート( 再起動 )する必要がある。そのための具体的なアクションを3つの主体に提言したい。
博士課程を「研究者養成コース」から、「社会のあらゆる領域で活躍する高度専門人材育成コース」へと再定義せよ。ビジネススクールや他学部との連携を強化し、アントレプレナーシップ教育を必修化するなど、カリキュラムを抜本的に改革すべきだ。給付型の奨学金を大幅に拡充し、多様な背景を持つ人材が挑戦できる経済的基盤を整えることも急務である。
博士人材を「専門職」として塩漬けにするのではなく、経営の中枢に登用する覚悟が求められる。博士が持つ論理的思考力や課題設定能力は、不確実性の高い現代の経営環境においてこそ価値を発揮する。まずは一人、博士号を持つ役員を登用することから始め、その知見が経営に与えるインパクトを可視化すべきだ。製薬業界に学び、グローバル基準の人事制度へと転換する必要がある。
法人税減税など、博士人材を雇用する企業へのインセンティブを強化すべきだ。だがそれ以上に、「博士とは、5年で陳腐化する知識を持つ者ではなく、一生使える思考法を体得した者である」という社会全体のパーセプションを変えるための、力強いメッセージを発信することが重要だ。科学者や研究者を尊び、その「知」こそが国富の源泉であるという文化を、国家の意志として再構築しなければならない。
「博士が輝ける国」は、間違いなくイノベーションが次々と生まれる国だ。失われた30年とは、日本が「知」へのリスペクトを失った30年でもあった。今こそ、その過ちを正し、博士を再評価することから、この国の再起動を始めよう。
【第5回】では、これらすべてのイノベーションの大前提となる「卓越した知」を生み出す博士人材が、なぜ日本で正当に評価されないのか、その構造的な問題に切り込み、「失われた30年」を終わらせる日本再生計画を提言した。最終回となる【第6回】では、産学連携の現場で生じる根源的な「断絶」——大学と企業の異なる制度ロジックの対立——を乗り越え、成功を収めるスター・サイエンティストの巧みな交渉戦略を、九州大学の安達千波矢教授の実践を通じて解き明かす。