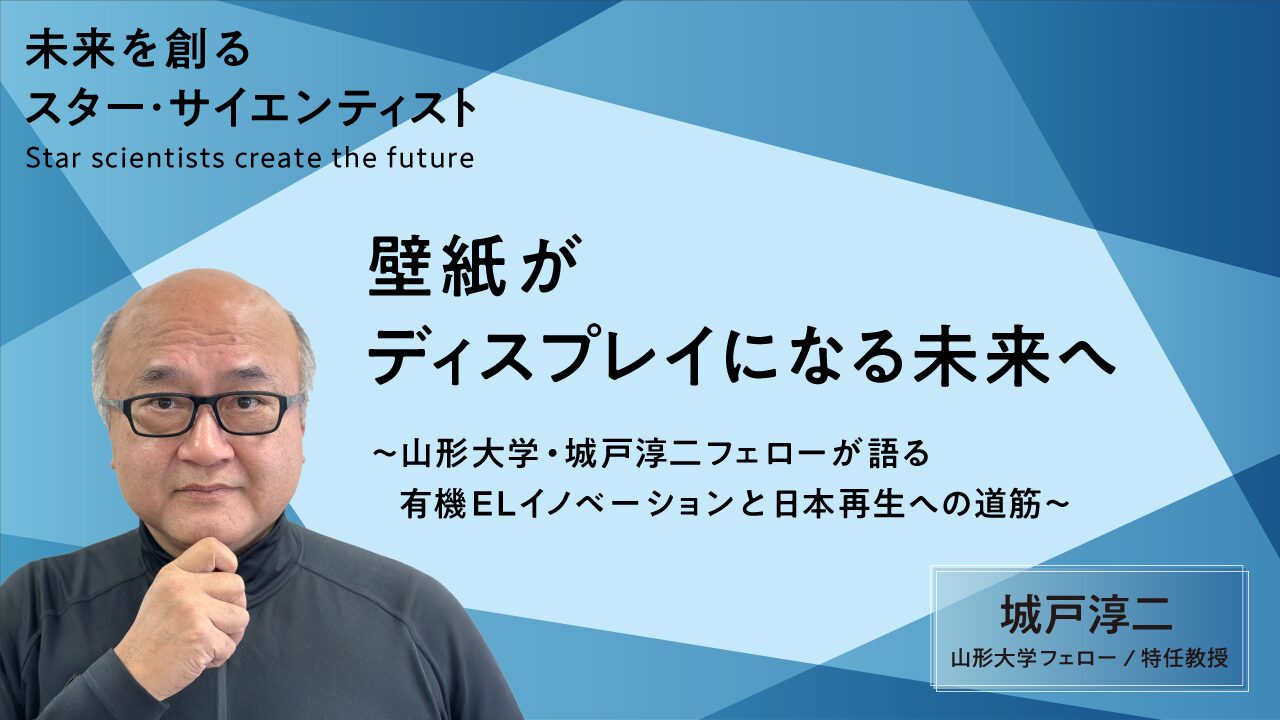

城戸 淳二
山形大学フェロー / 特任教授
目次

山形県米沢市。人口8万人弱のこの地方都市に、世界の有機EL研究をリードし続ける研究者がいる。山形大学の城戸淳二フェロー(特任教授)だ。35年以上にわたって有機ELの研究開発に携わり、その実用化と産業化を推進してきた城戸氏は、単なる研究者の枠を超えた存在である。大学発ベンチャーを次々と立ち上げ、地域産業の活性化に貢献し、次世代の人材育成にも情熱を注ぐ。その活動は、まさに「スターサイエンティスト」と呼ぶにふさわしい。
2025年5月と8月に行われた長時間インタビューで、城戸氏は日本の産業が直面する危機、研究開発の本質、そして未来のビジョンについて率直に語った。その言葉には、地方から日本を、そして世界を変えようとする強い意志と、長年の経験に裏打ちされた深い洞察が込められている。
城戸氏の研究人生は、実は偶然の連続だった。早稲田大学応用化学科に進学したのも「親孝行のつもり」で、化学は大嫌いだったという。父親がプラスチックの成形加工の町工場を営んでいたからだ。「講義にもほとんど行かなかった。馬場から西早稲田まで25分も歩かなきゃいけないし、大教室で先生がボソボソ何か言ってるだけで、1回行ったらもうええわ、みたいな」と当時を振り返る。
転機は4年生の研究室配属だった。土田英俊研究室で初めて触れた最先端の研究の世界。「高分子でも有機物でも、分子設計して合成したものって、今まで地球上に存在してなかったものなんですよ。それに気がついて、自分の手の上に乗ってるこの白い粉って、地球上で俺が初めて手にしたもんやって。ワクワクしますよね」
その後、研究者として自分の力を試すべく、ニューヨーク・ポリテクニック大学(現ニューヨーク大学)への留学を経て、1989年に山形大学工学部の助手として着任。その留学先で出会ったのが有機ELだった。試薬棚で見つけた透明のアクリル樹脂。発光性の希土類化合物が少量分散してあり、紫外光を当てると真っ赤に光り輝いた。おいおい、このプラスチックを電気で光らせることができたら世界が変わるで、と有機物を電気で光らせることに興味を持った。
「蛍光ペンってあるじゃないですか。あれ有機物の蛍光物質ですよ。紙の上で書くと室内の蛍光灯の光で刺激されて、ほんのり光ってるでしょ。我々の有機ELで使う材料も薄膜にして、紫外線照らすとほんのり光るんですよ。けどね、それを電極で挟んで電気流したらめちゃ眩しくぐらい光るんですよ。もうびっくりしましたよ」
城戸氏が語る研究の醍醐味は、まさにこの「予想を超える瞬間」にある。最初はぼんやり光っていたものが、工夫を重ねるごとに明るくなっていく。有機ELの研究って、とにかくおもろい。その過程で感じる「おもろい」という純粋な好奇心こそが、研究を続ける原動力となった。
城戸氏は1993年に世界で初めて白色発光の有機ELを発表し、その後、2003年には発光ユニットを多段化するタンデム化にも成功、高輝度で駆動しても長寿命という画期的な素子構造を生み出した。これは有機EL分野の三大発明の一つと言われている。
そして、2008年、城戸氏は三菱重工、ローム、凸版印刷、三井物産という日本を代表する4社と共同で、有機EL照明パネルの製造・販売を行うルミオテック社を設立した。大学教授が事業計画を考え大企業をまとめるという異例の展開だった。
「例えば日本の会社が単独で有機EL照明事業化します、ぜひ一緒にって言われて手伝ったとしても、いずれサムスンとかLGとか出てくるし、中国が出てきた時に絶対そんな会社は負けると。1対1でやったら間違いなくサムスンに負けるんですよ。投資の規模、速さは、サムスン強いです」
そこで城戸氏が考えたのが、各社の強みを結集する戦略だった。三菱重工の真空蒸着技術、ロームの有機EL技術、凸版印刷の印刷技術、三井物産の販売網。これらを組み合わせることで、韓国・中国勢に対抗しようとした。
「三井物産と三菱重工が合弁作るなんていうのは、多分最初で最後です。これは他の大学の先生にはできないし、多分やろうともしないですよ」
しかし、ルミオテックは期待通りには進まなかった。最大の問題は投資の規模と継続性だった。
「最初はパイロットプラントで30センチ角の基板でまず、それでも10億、20億ぐらいかかったのかな。で、まずパネルっていうものを世の中に出さないと、有機EL照明っていうのがどういうのかみんな知らないし。で、行けるとなったら、でかい基板、1メーター角の基板でライン作って安くしてみたいな、そういう計画だったんです」
しかし、大規模ラインには100億円規模の投資が必要だった。企業の担当者が変わるたびに「100億ですか…」となり、結局、中途半端な投資で終わってしまった。
「技術があるのに、投資が中途半端で負ける。いい例ですよ」
城戸氏の発明した白色タンデム素子が照明だけではなく、カラーフィルターと組み合わせて大型テレビに応用され、その市場が拡大してる現在、城戸氏が考える次の展開が「プロセスイノベーション」だ。従来の有機EL製造は真空蒸着技術を使うが、これには致命的な問題がある。
「大画面ディスプレイの製造するために基板サイズがでかくなると、製造装置がデカくなるんです。有機半導体を真空蒸着するために巨大な真空チャンバーが必要で、しかもそれが10個、20個繋がってるから、それこそ戦艦大和みたいな工場ですよ。電力消費が大きくて、真空蒸着って材料を蒸発させるんですけど、蒸着機の内壁とかにいっぱい付くんで、実際に基板に付着する分って少ないですよ。とにかく、プロセスが無駄の塊で、それこそサステナブルじゃないんですよ」
城戸氏が目指すのは、すべてを印刷で作ることだ。
「インクジェットは、いるところにだけポタッて落とすから材料無駄にならないんですよね。しかも製造装置自体がすごくコンパクトになる。設備投資が小さくて、製造コストも安い、オール印刷で壁紙テレビを作るっていうのが私の、というか人類の究極のゴールなんですよ」
城戸氏の開発思想は徹底している。技術開発の後に価格を決めるのではなく、最初に売値を決めてから必要な技術を考える。
「65インチのペラペラのディスプレイができました。はい、これ5千万円です。売れないですよ。これを20万円で例えば量販店で販売するためにはみたいな、こうやって最終的に工場出し5万円、それを実現するにはどういった技術がいるって、そっちから考えないと」
この発想は、多くの大学研究者とは真逆だ。「大学の先生でそんなこと考えてる人ほとんどいないんですけど、私は製造方法含めコストを考えないと基礎研究ならともかく、応用、実用化を目指すのであれば全然意味のない研究になっちゃいます」
城戸氏が描く未来は壮大だ。壁紙ディスプレイはまだ通過点に過ぎない。
「最終的にはもう脳に電気信号を直接入れるようになリますね。これは絶対そうなるんですよ。人間の目、網膜なんて所詮カメラみたいなもんで、光を電気信号に変換して、脳に送られて、脳でそれをプロセスして映像として認識するわけで、だったら脳に直接電気信号を送ればって話なんですよ」
この技術が実現すれば、目が見えない人でも見えるようになる。さらに、脳の活動を電気信号として記録できれば、夢を録画することも可能になる。
「国家プロジェクトのムーンショットでそれ提案したんですけど、落とされましたけどね。技術的にはもう30年ぐらいで可能になると思います」
「しかもその応用として、脳で考えたことをそのまんま電気信号にして相手のスマホに送って、さらに脳に送れますから、テレパシーみたいなことができるはずなんです。原理的には絶対に可能です」
城戸氏が描くのは、視覚だけでなく、音も匂いもすべてが脳への直接信号で伝達される世界だ。フレキシブルエレクトロニクスと脳科学の融合により、人類のコミュニケーションは根本的に変わる可能性がある。
城戸氏は日本の製造業の現状に強い危機感を抱いている。
「この30年、賃金が上がらないし、韓国、それから中国に製造業は負けましたよね。ああいった国の企業って国のバックアップを得てどんどんでかい工場作っていくんですよ。一方、日本は撤退撤退でしょ。残ってんのは車だけ、トヨタだけみたいな話になったんですよね」
特に中国の動きは脅威だ。「各省がね、誘致合戦するわけですよね。その時にここの工場建てたら、例えばその500億の250億を省が出すみたいな話になったりして。どんどん工場もでかくなっていくし。もう日本もう勝てないですよ」
投資規模だけでなく、意思決定のスピードも問題だ。
「昔は松下でもどこでも、首をかける事業部長っておったわけですよね。社長に直訴して、金持ってきて色んな新しい事業に挑戦する。今そんなのいないですよ。上から言われたことをやるようなサラリーマン事業部長ばっかりなんで」
研究開発の面でも、日本は構造的な問題を抱えている。
「昔から国の研究費の半分は東大に行って、その半分が旧帝大にまわり、残りの半分を地方大学で分けてるみたいなところがあって。しかも、旧帝大にはベンチャーキャピタルが整備されてて、例えば東大の先生がね、なんか特許出したとか言うと、すぐベンチャーできちゃいますからね。地方大学はその点で難しいんですよね」
定年後も山形大学に残り、「未来創造ラボ」を立ち上げた城戸氏。そこで行う「城戸塾」は、1年生を対象とした少人数制の特別プログラムだ。
「高校生って夢を持って大学に入学してくるんですけど、興味のない教養の授業を受けて面白くねえなみたいな話になって、バイトやってサークル活動やって学校来なくなって道を踏み外してるケースがすっごい多いんですよね。全国的にもね。」
城戸氏は1年生の最初の1ヶ月が決定的に重要だと強調する。「今まで中高って先生が手取り足取り教えてるわけですよ。宿題しなかったら叱られるし、学校来なかったら来いよって言われるし。それが大学に来たらもう誰も指導してくれる人がいない」
城戸塾で重視するのは「物の見方」「視点を変える」ことだ。
「テーマを与えてそれに関して3分間プレゼンをして、それに対して私がああやこうや言うみたいな感じですね。特に強調してるのは物の見方っていうか視点を変えるっていうか。発明っていうのは大体そういったところから生まれるし」
また、プレゼンする際に聞き手を意識することの重要性も教える。「講演会行く時はまず誰が聞いてるのか。まず聞き手が誰なのか、それをよく考えてくださいっていうことは必ず言ってます」
理系人材を増やそうと、ようやく国は動き始めたものの、城戸氏は、よくある「科学マジックショー」的なアウトリーチ活動を批判する。
「ミスターマリックのマジックショーを見てマジシャンになりたいかっていう話なんです。見てておもろいけど、そうなりたいって違うんです。やっぱり一流の研究者の話を聞く、直に話をする。その熱い思いが伝わらないと、そうなりたい、科学者になりたいと思わないでしょう」
城戸氏自身、高校や中学の出前授業は頼まれれば断らない。札幌の高校には10年近く毎年出前授業に行っており、そこから山形大学に進学する学生も多い。重要なのは、研究の面白さだけでなく、研究者の生き様を伝えることだ。何がきっかけだったか、などね。
「子供の頃の成績表あるじゃないですか、通知簿。母親が取っておいてくれたんですけど、それをパワポでバンバンバンと出して、いや実は俺勉強嫌いやったで、みたいな。で、なぜ勉強嫌いで研究者になれたかっていうその経緯を話してあげると、じゃあ僕も私もなれるかもってなるんですよね。エリート学者の経歴って全然参考にもなりませんから。」
城戸氏の研究哲学の根底には「ゼロスタート」がある。有機ELの研究を始めた時、半導体の知識はゼロ。真空蒸着装置の操作も知らなかった。そもそも有機ELの研究分野というものすらなかった。
「最初、学生とディスカッションするときでも、偉そうになんでも知ってるみたいな顔で話しますますけど、実は自分自身、興味はあるけど何も知らないですよ。そういうゼロからのスタートでやるっていうのが、結構私、平気っていうか、慣れてんですよね」
この姿勢は、3浪して早稲田大学に入った受験時代に培われた。3浪といってもまともに受験勉強したのは3浪目だけ、「1日16時間勉強した。その時に数学はこうやろう、英語はこうやろうって自分で勉強方法みたいなのも編み出して。誰かに受験勉強法を教えてもらうとか、塾とか予備校でこうやりなさいって言われてやったわけでもなくて、自分で考えて実行しただけなんです」
「ブレイクスルーって何をぶち破るかわかりますか? 私にとってのブレイクスルーって、それはもう常識をぶち破ることです」
城戸氏は、一つの研究分野に長くいると、その分野の常識にがんじがらめになると指摘する。「けど、ちょっと視点を変えてみるとね、あれ、それっておかしくない、みたいな。こっちの分野の人間からしたら、それはおかしいよ、もっと別の見方をすると」
「応用化学科の先生は材料合成しました、こんな物性です、それで終わっちゃうし。電子情報系の先生がやるとデバイスしかやりません。自分の守備範囲は半導体だからそっちだけで、合成なんかとてもやりません、みたいな」
城戸氏は材料合成もデバイス開発もプロセス開発もすべて手がける。この守備範囲の広さが、2002年にNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の有機ELプロジェクト(5年間で55億円)のリーダーに選ばれた理由だった。
NEDOの国家プロジェクトが始まると、山形県はその成果を地域の産業に活かしたいと城戸氏の研究に7年間で43億円を投資した。しかし、それに比べると米沢市からの支援はほぼゼロだ。
一方、慶應義塾大学先端生命科学研究所がある鶴岡市は毎年数億円規模を約20年以上出し続けている。「あのくらいあったら、俺、ベンチャー20社くらい立ち上げてるわ。金があるっていうことは、優秀な人材をいくらでも引っ張ってこれるんですよ。鶴岡が羨ましいですね。」
ものづくり系ベンチャーとして鶴岡のスパイバー社は日本のバイオベンチャーの成功例として語られることが多いが、城戸氏は懐疑的だ。
「えっ、成功例なんですか、みたいな感じですね。だってまだ上場もしてないし、少なくともまだ黒字化してないし。私は高分子化学の人間で、高分子とか繊維とかの専門家でもあるんですけど、そもそもこれ安くできるのって。技術的には面白いんですけど、どうしてもコストのことを考えてしまいますね」
アメリカのSBIR(Small Business Innovation Research)制度と日本の制度の違いは金額だけではない。
「アメリカってSBIRっていう制度があって、例えば基礎的な段階でも特許出せば、ベンチャーってできるんですよね。フェーズ1なんて言うと、研究開発費の助成金が年間2〜3000万円出るのかな。もちろんこれでポスドクを雇って2、3年間くらい技術の成立性をチェックする。実用化行けそうと評価されるとフェーズ2ですよ。2〜3億円の助成金で実証実験、そして最終的には実用化研究でフェーズ3です。その頃にはVCや企業が絡んで従業員も数十名でしょうか。」
日本の問題は、制度だけでなく人材だ。「そういったベンチャー経営者、CEO屋さんがアメリカにはいっぱいいるっていうことなんですよね。技術わからなくっても、CTOを引き連れて、俺はこの技術で会社運営経営して、金なんか知り合いのキャピタルから何ぼでも持ってくるわ、みたいなやつが、うじゃうじゃいてるんですよね。ベンチャーで成功することがアメリカでは理系のゴールとも思われてる」
「だから、ベンチャー5年間やって失敗しても、じゃあ次行こうぜみたいな感じ。で、その間5年間は給料しっかりもらって。だから誰も不幸になんないですよ、ベンチャー失敗しても」
一方、日本では「失敗したらああああみたいな。それから銀行から金借りる時に、保証人になって社長さん大体家屋敷担保に入れるみたいな。こんなのじゃ絶対誰もベンチャーなんかやらないし」
「やっぱり100に1つ当たるんですよね、結局ね。ユニコーンを作るっていう目的で、いかに数を作ってその中から成長させていくか。イーロン・マスクも、電気自動車やるぜ、みたいな感じで、VCがじゃあ金出すよ、みたいになるじゃないですか。で、あそこまででかくなるんですよね。最初は何の先端技術もない単なるかっこいいだけの電気自動車ですよ。日本じゃ絶対に無理だったでしょうね」
城戸氏は、イノベーションの源泉は好奇心にあり、それは環境に大きく左右されると考える。
「子供たちはみんな好奇心旺盛なんですよ。育つ中でそれに蓋をしちゃってるんです。それをやっぱり解放させて体験させるっていうのが、イノベーターを生み出す上で非常に重要かなと思う。そういう意味ではね、この田舎暮らしがいいんですよね。自然の不思議、何だろうこれっていう現象、体験がもうあちこちに、普通に身の回りにあるんですよ」
興味深いデータがある。日本のノーベル賞受賞者20数名の出身高校を見ると、ほぼ全員が県立高校か府立高校の出身で、東京の進学校出身者は1人もいない。
「ハッキリ言って進学校に行けば行くほど好奇心を失う教育されるってことです。東大行くための勉強ばっかりするんですよね。そんな子供たちはウルトラクイズは解けても好奇心が旺盛じゃない。」
城戸氏の好奇心の原点はものづくり、実家のプラスチック成形加工の町工場にある。
「元々プラモデル作るのが小学校の時大好きでね、プラモデルばっかり作ってましたよ。ラッカーで色塗るじゃないですか、シンナーとか使うじゃないですか。あの匂いずっと嗅いでたから、それでアホになったんちゃうかな」
このものづくりへの愛着が、後の「パソコンだけで儲ける人は嫌い」という価値観にもつながっている。
城戸氏の研究は有機ELディスプレイから照明へ、そして睡眠研究へと展開している。筑波大学の柳沢正史教授との共同研究では、光が睡眠に与える影響を研究している。
「私が究極的に考えてるのは、睡眠をコントロールできないかなと。5時間の睡眠ならその5時間をどう有効に使って最大限の睡眠を取らせるか。それを外部刺激、光であったり、音であったり、温度であったりで。睡眠効率を高めるということですね。」
実験では、光による覚醒が睡眠満足度に大きく影響することが分かっている。「ジリジリジリっていう音で起きると気分悪いです。ところが、日の出のような感じで光で目覚めると、すごい快適なんですよね」
城戸氏は、臨死体験で多くの人が光を見ることに着目する。
「日本人だろうが西洋人だろうが、宗教に関係なくみんな光見る。なんで光を見るのかと思って考えたら、人間おぎゃあって生まれて最初に光を見るんですよね。光に始まって光に終わるみたいなところあるんじゃないかなと思います」
城戸氏は日本の定年制度に強い憤りを感じている。
「アメリカなんかね、私の恩師は95歳まで、死ぬまで研究やってました。普通でしょ、外国みんなそうなんですよ。日本だけ65歳、はい、研究室もないです」
これは単なる個人の問題ではない。「他にも有名な、我々同世代で有名な研究者いっぱいいるじゃないですか。それが、定年になったら、わけのわからん私学に行って授業だけやってますって、もったいないですよね」
「第2の城戸を育てろ、みたいによく言われるんですけど、それって無理ですよね。大谷翔平に第2の大谷翔平を育てろっていうのと同じで、これ絶対無理なんですよ。大谷翔平は大谷翔平として生まれてきて、環境がその才能を伸ばしたわけです。我々ができることって、そういう研究者が育つような環境を整えておくことしかできないんですよ」
しかし、その環境づくりも継続性がない。「学長変わるし、学部長変わるし、大学も環境が変わりすぎる。文科省の大型プロジェクトも継続性ありませんしね。特に地方大学は疲弊してますよ」
インタビューでスター・サイエンティストと呼ばれることについて尋ねられた城戸氏は、意外な答えを返した。
「スターじゃないですよ。全然スターじゃない。やっぱり山中先生みたいな人かな、私から見たらスターっていうのは」
城戸氏は自身を「研究者じゃない」とさえ言う。「元々大学の先生になるなんて1ミリも考えてなかった。人前で喋るのができなかったですよ。今じゃ想像つかないでしょうけど」
「自分自身は自由人みたいな感じなんですよ。サイエンティストかって呼ばれると、うーん、そうかなって思う時ありますよね。プラモデル好きの子供が、大人になって有機ELの研究に没頭しただけなんですよ。私はいらんこともいっぱいやってる。睡眠もやったりとか、食いもんのこともやってたりとか」
しかし、まさにこの「いらんこと」への関心の広さが、城戸氏の強みであり魅力だ。牧氏は「そういう点が魅力でコミュニティが広がっていくし、社会へのインパクトってそういうところから生まれるのでは」と指摘する。
城戸氏にはもう一つの顔がある。日本一のすき焼き屋を作ることが「直近の目標」だという。
「米沢は牛肉の店が多いんだけど、やってるオーナーがそこまで牛肉好きじゃないんじゃないかと。米沢牛愛が足りない。親父の後継いだからだからやってますみたいなね。サウナのオーナーがサウナ好きじゃないのと一緒です」
この食への情熱は、単なる趣味を超えている。味覚とは何か、いかに美味しく食べてもらうか、という探究心は、研究への姿勢と共通している。
城戸氏は「ゴルフ好きの大学教授」としても有名だ。東京で紫綬褒章を受章した翌日、週刊ゴルフダイジェストの取材を受けた際、「編集者から、ネットで調べたら大学教授でゴルフ好きは、先生がトップに出てきたんです」と言われたという。
「世の中、人によっては、城戸は単にゴルフの好きな先生と思われてたりね。まあ、それもいいんですよね、本質的には。ただ、後で僕有機EL研究者なんですけどみたいな、後で付け加えないといけないんです」
城戸氏が目指す「壁紙テレビ」は、もはや夢物語ではない。スマートフォン用の有機ELラインは既にG6.5ハーフ(約3メートル角)まで大型化している。技術的には実現可能だ。問題は、いかに安く作るかという一点に絞られている。
「オール印刷で壁紙テレビを作る」——この究極のゴールに向けて、城戸氏は今も研究を続けている。しかし、それは通過点に過ぎない。その先には、脳に直接信号を送る時代、テレパシーが当たり前になる世界が待っている。
山形県米沢市。人口8万人弱のこの地方都市から、城戸氏は世界を変えようとしている。地元からの支援は限定的で、優秀な人材も集まりにくい。それでも諦めない。
「優秀な人材っていうのが圧倒的に少ないわけですよ。でも、だからこそやらないといけない」
城戸氏の挑戦は、単なる技術開発ではない。日本の産業を再生し、次世代の研究者を育て、地方から世界にイノベーションを起こすこと。それは一人の研究者の枠を超えた、日本の未来への挑戦だ。
「ブレイクスルーって、常識をぶち破ることです」
城戸氏の言葉は、すべての研究者、起業家、および未来を変えたいと願うすべての人へのメッセージだ。常識にとらわれず、視点を変え、ゼロから始めることを恐れない。失敗を恐れず、100に1つの成功を目指して挑戦し続ける。
壁紙がテレビになる日は、そう遠くない。しかし、それは始まりに過ぎない。城戸淳二という一人の「自由人」が描く未来は、私たちの想像をはるかに超えている。その実現に向けて、今日も山形の地で、新たな常識の破壊が始まっている。
インタビューの最後、城戸氏は若い世代へのメッセージを語った。
「まず自分の専門で1番になる。そうすると、この分野にはこの人がいるんだって他の分野の人も知ってくれる。それから興味のあることをどんどん横展開して、興味の幅を広げていく」
そして、最も重要なこととして、好奇心を失わないことを挙げた。
「好奇心は生まれ持ったものじゃなくてトレーニング可能です。子供たちはみんな好奇心旺盛なんですよ。育つ中でそれに蓋をしちゃってる。それを解放させて体験させることが重要です」
城戸淳二、66歳。その瞳には今も、初めて有機物が電気で光った時と同じ輝きがある。「おもろい」と思う気持ち、それこそがすべての始まりだ。壁紙がテレビになる未来も、脳に直接信号を送る時代も、すべてはその純粋な好奇心から生まれる。
日本の未来は、決して暗くない。城戸氏のような研究者が、地方の片隅で世界を変える技術を生み出し、次世代を育てている限り。常識を破り続ける者たちがいる限り、日本のイノベーションは止まらない。